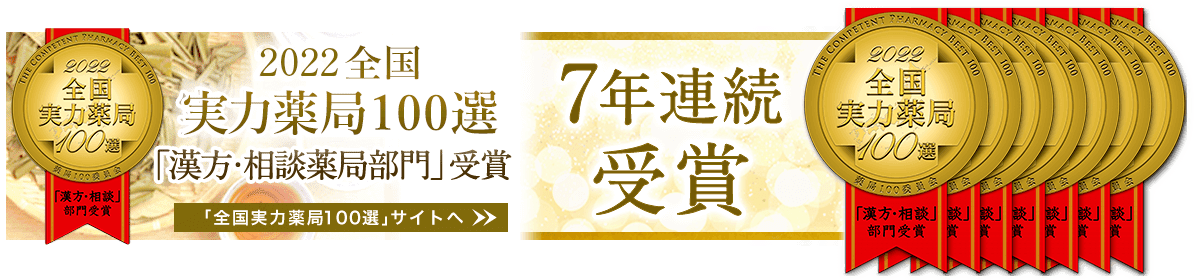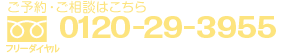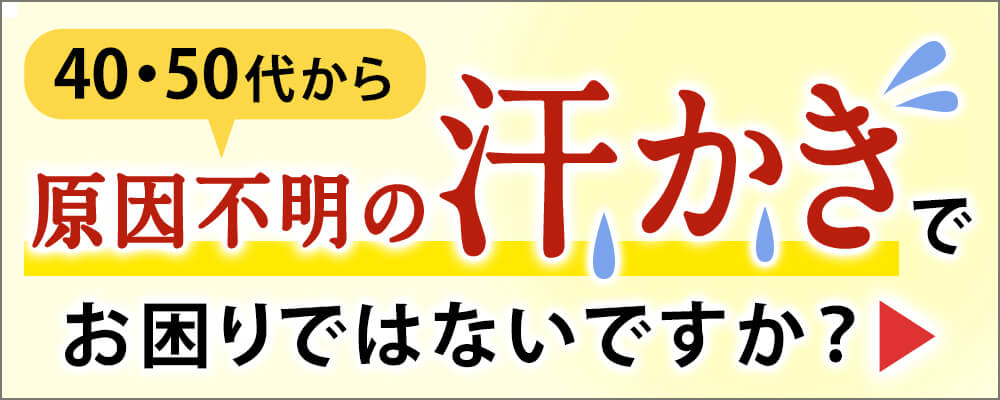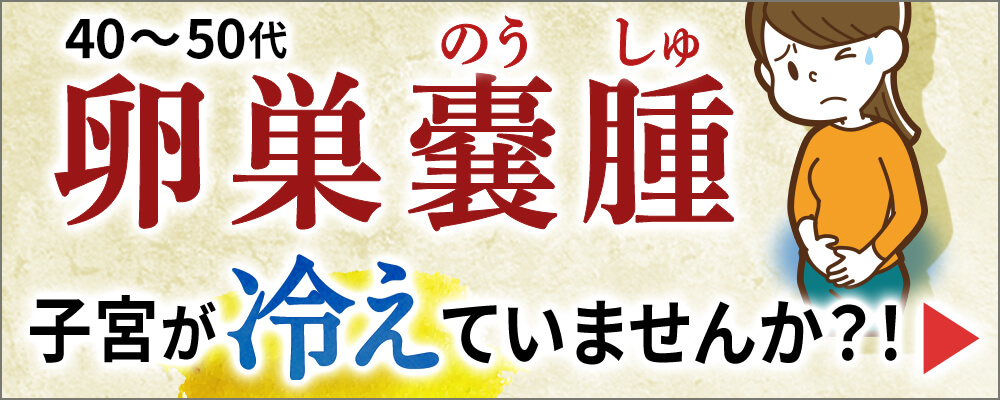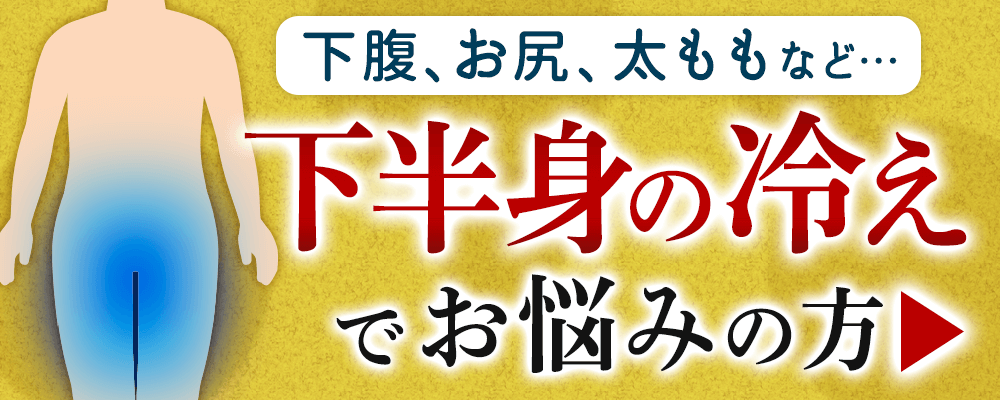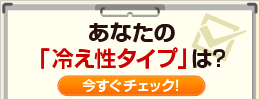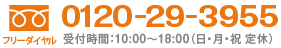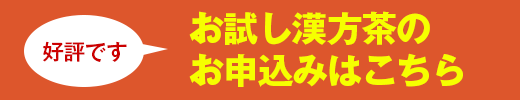冷え性は放っておくと、特に40~50代から顕著な体調不良となって現れますので、軽く見ないで早めに改善していきましょう。
あなたの身体にこのような症状があったら、冷えが原因かもしれません
疲れやすい、めまい、頭痛、肩こり、耳鳴り、鼻炎、花粉症、不眠、イライラ、うつ、神経症、低血圧、貧血、風邪をひきやすい、食欲不振、胃炎、便秘、下痢、腹痛、お腹のハリ、腰痛、下半身の冷え、下半身太り、太りやすい、不妊、生理不順、生理痛、子宮筋腫・卵巣嚢腫などの婦人科系疾患、むくみ、汗かき、のぼせ、動悸、肌荒れ、頻尿、膀胱炎、足がだるい、手足のしびれ、手足の冷え、手足のほてり…
冷え性の原因
東洋医学からみた冷え性の原因
「気・血・水」がまんべんなく身体を循環することが、健康の基本と考えます。
冷え性には、4つのタイプがあります。
1.気虚-エネルギーが不足しているタイプ。
2.血虚-全身を流れる血液が不足しているタイプ。
3.瘀血-血液がドロドロして滞っている状態。中高年以降、瘀血が増える傾向があります。
4.寒湿-水毒を持っているため身体が冷え、むくみ、めまいになりやすいタイプ。
血液の流れからみた冷え性の原因
髪の毛1/10程度の太さといわれている毛細血管の血流は、体温を維持するために重要な働きをしています。熱を生み出している筋肉に、酸素や栄養を運び老廃物を運び去るのは血液で、毛細血管を介して行われています。血液は温かく、冷たい外気にあたると手足の血管を収縮させて熱を逃がさないようにしています。加齢や運動不足、ストレスの影響で毛細血管の血流は低下、或いは毛細血管が減少するため、冷えるようになります。
自律神経からみた冷え性の原因
深部体温を37.2℃に保つために、身体を活動させるアクセル役の交感神経と、リラックスさせるブレーキ役の副交感神経があり、お互いがシーソーのようにバランスよく働くことで、体内の体温が保たれています。交感神経の過剰、或いは、副交感神経の過剰は、冷え性の原因になります。
ホルモンのバランスからみた冷え性の原因
ホルモンは、極微量でさまざまな身体の調整をしており、熱の産生や代謝にも深く関わっています。例えば、甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンは、代謝を亢進させて熱を産み出しています。ホルモンのバランスが乱れると、体温コントロールにも影響を与えるので、冷え性の原因になるといえます。
女性に冷え性が多い理由
女性に冷え性が多い理由として、次のようなことが挙げられます。
●熱を発生する筋肉が男性より少なく脂肪が多い為。脂肪は温まりにくい性質なので「太っているのに冷え性」という女性は多い。
●女性特有の生理で、貧血状態になりやすい。
●毎月の生理によるホルモンの入れ替わりは、ホルモンバランスの乱れの原因になります。また、更年期前後の女性ホルモンの減少は、他のホルモンにも影響を与えるためにバランスが乱れやすい状態です。これらが冷え性の原因になります。
●更年期以降は、女性ホルモンが減少するために、血液が粘つきやすくなります。それが冷えをしつこくさせる原因になります。
40代、50代以降に身体の不調が現れるのは
40代、50代になると、生命エネルギーである「腎」の力が衰え始めます。今まで積み重ねてきた無理、神経疲れやストレス、運動不足、体を冷やす食生活などの影響が体調不良となって、或いは病気となって現れやすくなります。親から受け継いだ体質も、この時期から現れ始めます。
冷え性に於いても、血液が粘ついてくる40~50代以降になるとガチガチで巡りの悪い根深い体質に進んでいきます。身体の無理が若いころのようにできなくなり、体調不良も治りづらくなります。